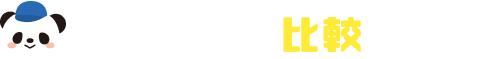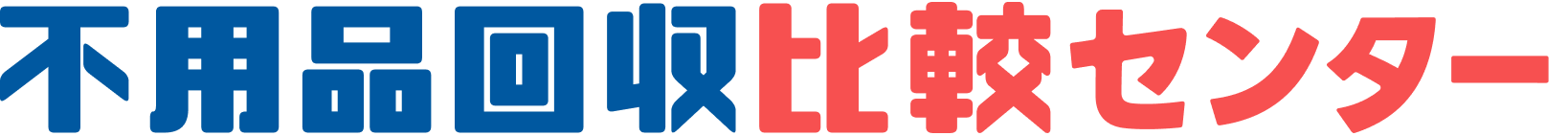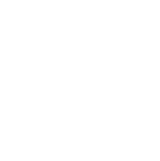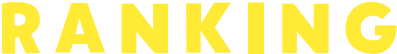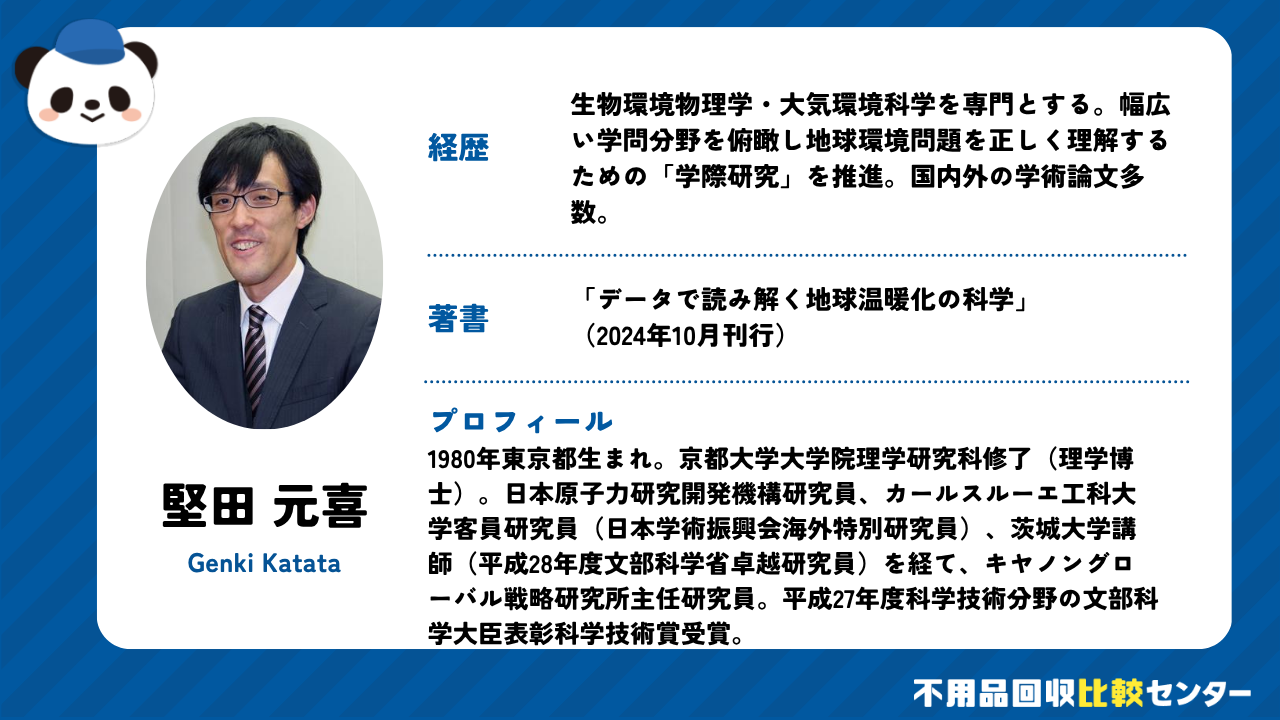
地球温暖化を研究する堅田元喜主任研究員へ著書に基づきインタビューしました
地球温暖化の好影響とは
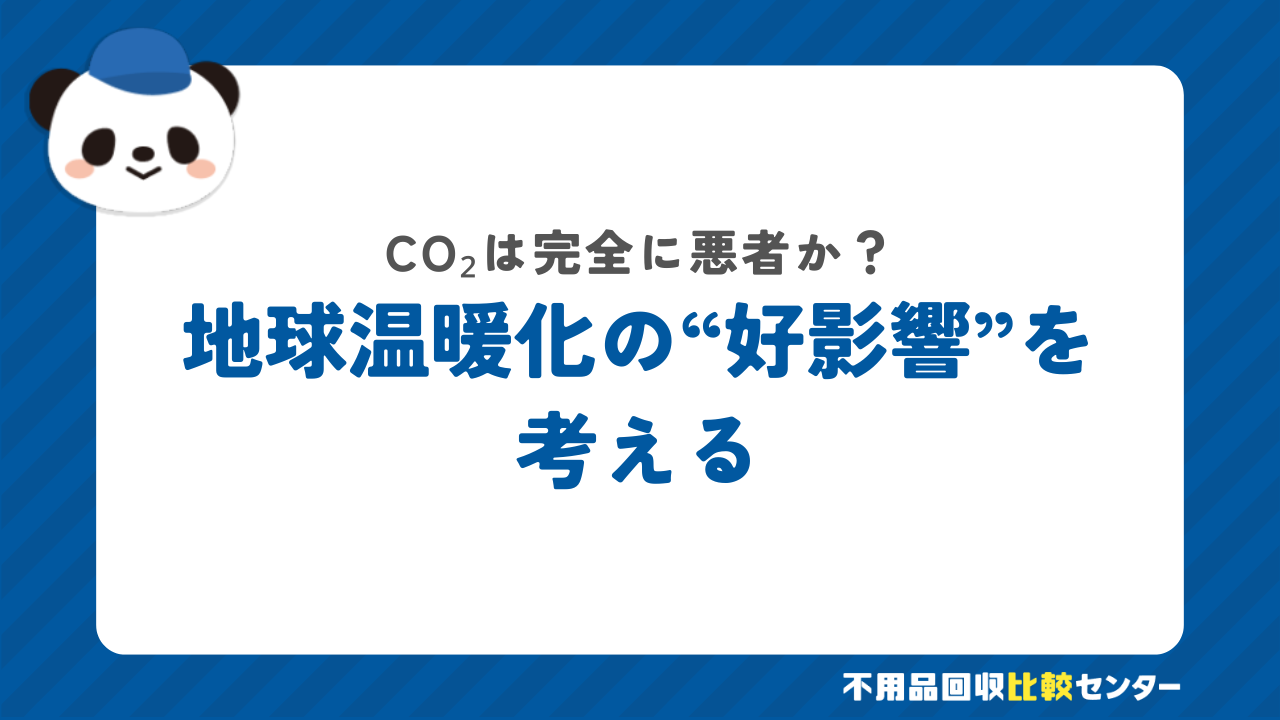
 パンダ回収隊長
パンダ回収隊長
書籍「データで読み解く地球温暖化の科学」についてお伺いします。先生は、地球温暖化の悪影響だけでなく、好影響についても言及されています。
具体的にどのような好影響があるとお考えでしょうか?また、それらの好影響はどの程度持続可能だとお考えですか?
気温上昇による農業生産性・生命活動の活発化などの好影響が挙げられますが、特に、高CO2濃度下で植物の光合成が促進するCO2施肥効果が重要です。これにより、農業生産性は大幅に向上しました。
衛星観測によると、21世紀に入ってから地球の土地面積の半分で緑化が加速し続けていますが、その主要因もこの効果です。CO2は現在も上昇し続けており、今後も好影響が期待できます。
また、人間に対しては、世界各国の都市で気温上昇により寒さによる死亡率の減少が見られました。
ヒートアイランドで冬の気温が1.5℃以上上昇した北極圏の都市では、寒さの緩和・海氷の後退・北方林の生態系の進化が進み、持続可能な都市環境が形成されつつあるようです。
 堅田元喜主任研究員
堅田元喜主任研究員
温暖化研究を支える数値シミュレーションの進化と壁
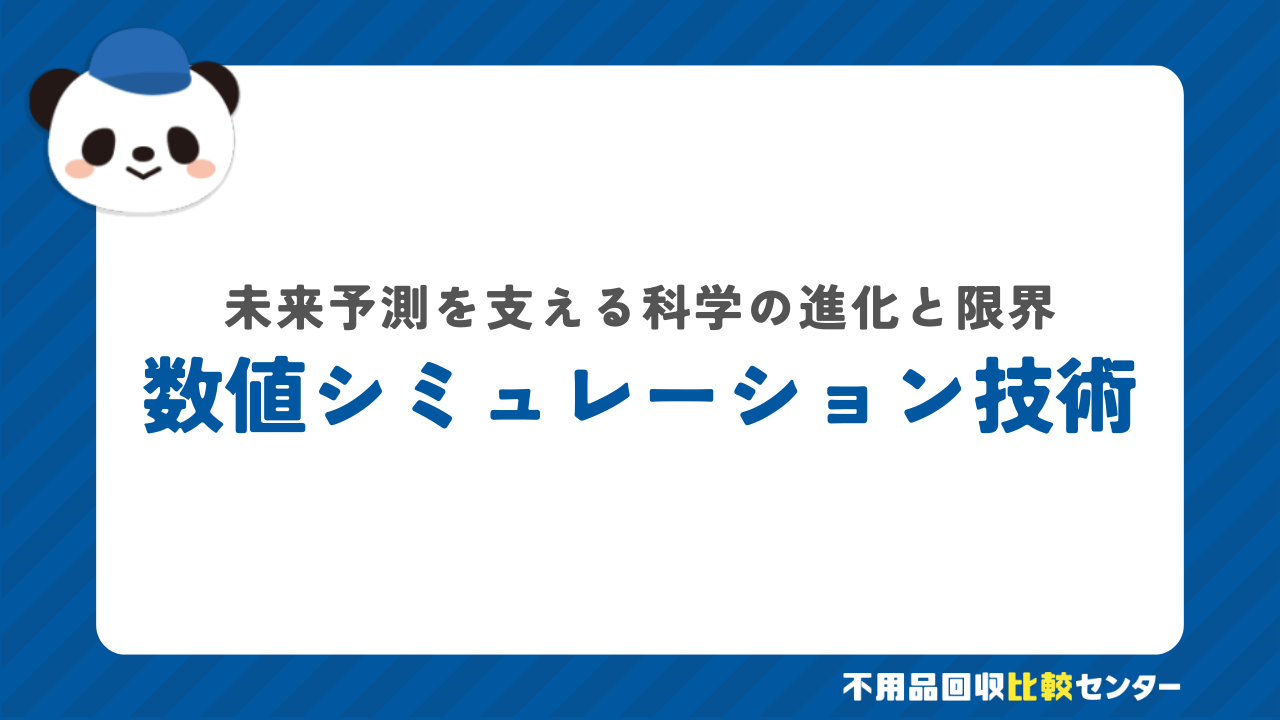
 パンダ回収隊長
パンダ回収隊長
数値シミュレーション技術の進展が、地球温暖化の理解にどのように貢献しているとお考えですか?
また、これらの技術の限界や課題についてもお聞かせください。
地球温暖化問題の理解は、シミュレーション技術の進展により飛躍的に深まったことは確かです。一方で、その再現精度には多くの課題も残っています。
例えば、気候変動に関する政府間パネルIPCCの気候シミュレーションでも、20世紀前半の温暖化現象(ETCW)を完全には再現できていません。
ETCWは、周期的に起こる太陽放射量の変動や地球の自然変動が引き起こした可能性があり、ここ数十年の温暖期にも影響しているはずです。
早急に解明しモデル化すべき問題ですが、観測データの不足がそれを阻んでいます。
また、農業のように予測困難な技術革新や社会変化(肥料・新品種の発明、都市化)などを将来シミュレーションに反映しきれない点も課題です。
 堅田元喜主任研究員
堅田元喜主任研究員
地球温暖化が人間や生態系に与える影響
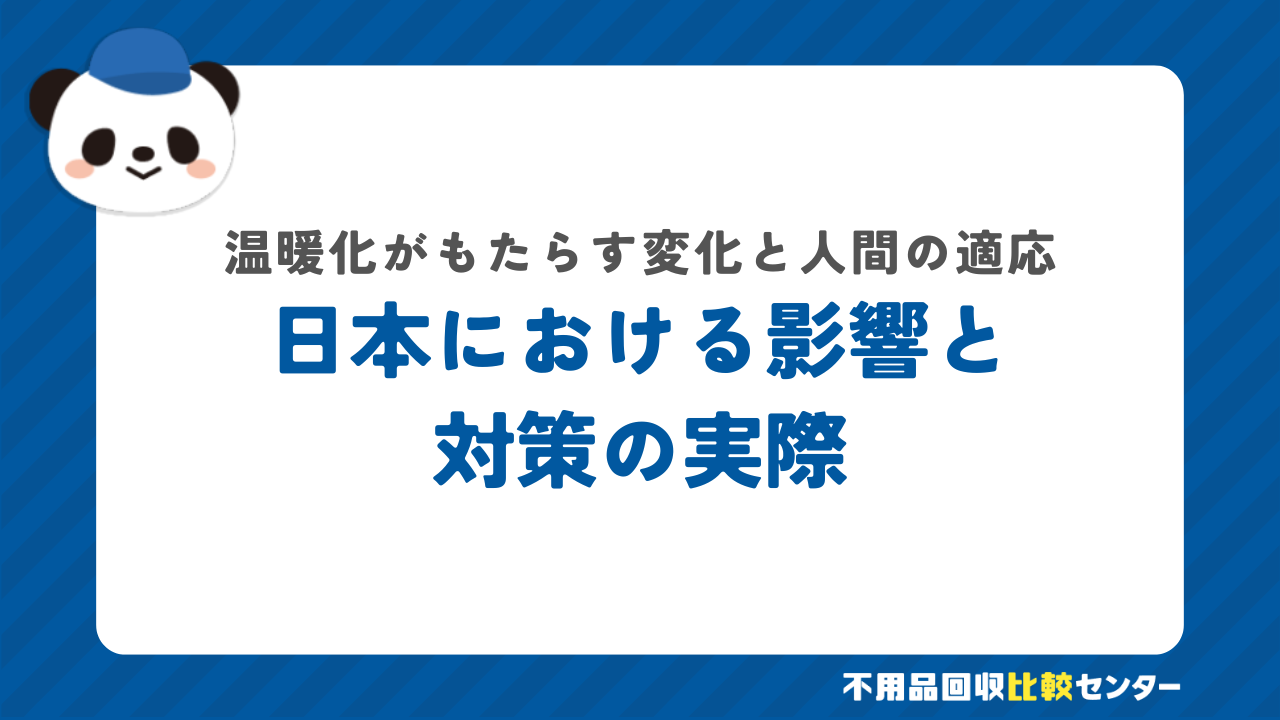
 パンダ回収隊長
パンダ回収隊長
地球温暖化が人間や生態系に与える影響について、どのように分析されていますか?
特に、日本における具体的な影響や対策についてお考えをお聞かせください。
温暖化の好影響は、日本でも見られます。その一方で、農林水産業では高温による農作物の品質低下などが深刻になるとされています。
しかし実際には、過去数十年の夏の気温上昇によるコメの収量低下はみられず、温暖年にはおおむね豊作でした。むしろ対策すべきなのは、温暖期の後に起こる寒冷期です。
例えば、温暖期に適した品種は、冷害に対しては不適になるリスクを持ちます。温暖な気候に過度に適応した社会は、その後数十年続く気温や降水量の急変に対応しきれず飢饉や紛争を経験したという過去の記録もあります。
本書籍では、このような逆境に対して能動的に適応してきた時代もあり、その際の経験を現代にも生かすべきであると述べています。
 堅田元喜主任研究員
堅田元喜主任研究員
地球温暖化問題に対する政策的な対応
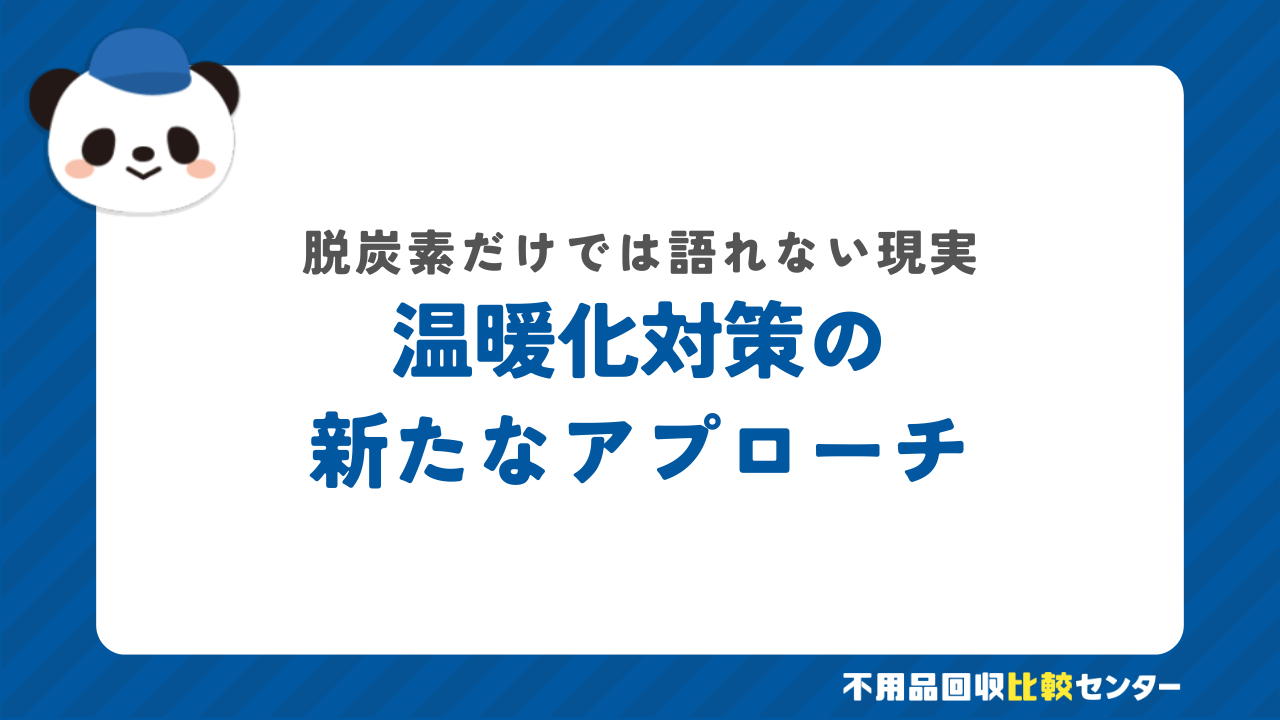
 パンダ回収隊長
パンダ回収隊長
前提となる考え方を変える必要があります。地球温暖化という現象は、未だ完全には解明されていない上、その影響であると誤解しかねない現象も多数存在します。
この考えに立って、仮にCO2排出をゼロにしても地球の気温が十分低下しなかった場合への対応策を用意すべきです。
具体的には、化石燃料の利用とは無関係に自然に起こりうる災害への対策です。
その方向性は、過去の温暖期(ETCWや都市ヒートアイランド)に起きた農業被害や災害に対する人間の自然発生的な対応策(適応策)を振り返ることで見えてきます。
また、根本的な対策とは別に、好影響であるCO2施肥効果を施設園芸農業に生かすことは、脱炭素一辺倒の視野を広げることに繋がるでしょう。
 堅田元喜主任研究員
堅田元喜主任研究員
今後の研究活動や出版予定
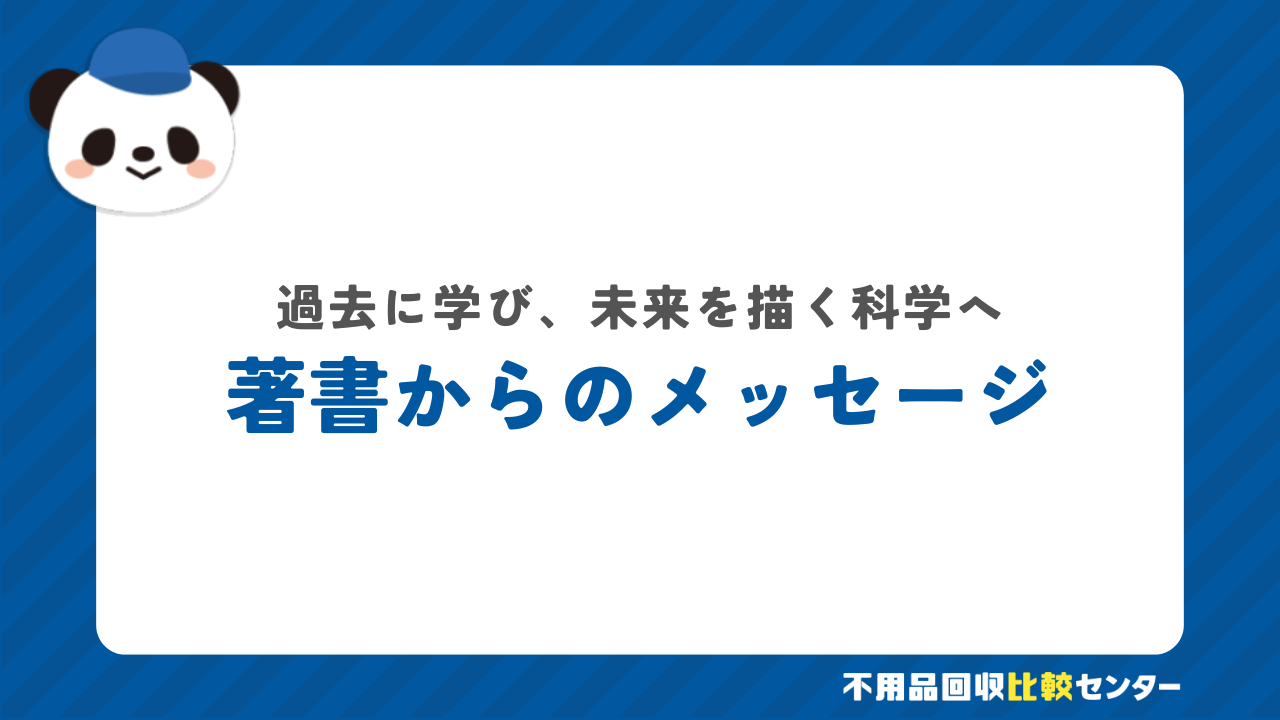
 パンダ回収隊長
パンダ回収隊長
先生が最も伝えたいメッセージは何ですか?
また、今後の研究活動や出版予定について教えていただけますか?
本書では、温暖化だけでなく様々な環境問題(水質汚濁、窒素汚染、花粉症など)も扱いました。問題の性質を理解し、未解明の問題を解くための考え方を示すためです。
自然現象とは、元来複雑なものです。思い込みによる一辺倒な対策は、逆効果になることもあります。
本書は、学生や若手研究者、温暖化対策を迫られている産業界や行政機関の関係者が、温暖化のリスクとベネフィットの両方を理解したいときに役立つと思います。
今後は、日本の過去の気候と適応の実態を理解するための研究コミュニティの形成や、古気候データベースの構築を推進する予定です。基礎研究の地道な積み重ねは、科学者の重要な役割だと信じています。
 堅田元喜主任研究員
堅田元喜主任研究員